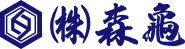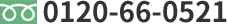日本瓦 メンテナンス工事のご紹介
- 2025.08.01
日本瓦のメンテナンス工事について、ご紹介いたします。
日本瓦自体は、愛知県産の三州瓦、兵庫県淡路島産の淡路瓦の2つの産地の瓦を三重県では主に使用しています。
どちらの瓦も1200度の高温で焼成している商品なので、商品自体は50年をはるかに超える耐用年数があります。
ただ、経年により、瓦がズレてしまったり、瓦の隙間を埋める漆喰が剝がれ落ちてしまったり、飛散防止用銅線が切れてしまったりと
そのような事由が原因で、雨漏りが発生してしまったり、瓦が飛散したりすることが見受けられます。
今回は、メンテナンス工事の種類や、なぜそのような工事が必要なのかについて、ご説明いたします。
① 漆喰


漆喰とは、瓦を施工する際に生じてしまう隙間を埋め、雨水の侵入を防ぐ工事内容です。意匠性だけではありません。
常日頃、雨水や紫外線、高温の状態にさらされる漆喰が、大体15年位が耐用年数だと思われます。
傷んでいる古い漆喰を全て除去後、セメント系の漆喰を使用し、工事を進めます。
② 棟部飛散防止用銅線巻き直し


銅線も経年劣化で線自体がやせ細り、切れてしまっている屋根が多く見受けられます。
銅線が切れていたり、無い状態で台風のような強風が吹いた際には、棟瓦が飛散することがあります。
そうすると、棟瓦が崩れたり、廻りの瓦や壁、窓、カーポートに被害が及ぶことがあります。
新しい銅線を用い、棟部を巻き直し、釘頭にコーキング処理を施します。
また、施工前に棟瓦自体のズレがある場合には、補修工事をおこないます。
③ 軒瓦、袖瓦 ステンレスビス留め




銅線で下地木材から、飛散防止、ズレ防止の目的で瓦に巻いてある銅線ですが、この銅線も経年劣化で切れてしまうことが多いです。
しっかり緊結していないと、強風が吹いた際、この袖瓦、軒瓦がズレたり飛散する被害が多いです。
既存の傷んだ銅線は除去し、ステンレス製ゴムパッキン付きのビスで、下地木材に留めつけます。
今回、ご紹介した工事内容は、多くご注文いただく内容です。
お伝えしたいことは、被害が起きてから工事をするのではなく、被害がおきる前にメンテナンス工事をしていただきたいという思いです。
被害内容によっては、軽微な工事で済まなくなるケースもたくさん見てきました。人間の身体と同じで、時々のメンテナンスは
必要です。屋根の上なので、目視で確認することは困難ですし、高所の作業になるので、屋根のプロにお任せください。
森亀では、瓦屋根診断士の資格を持つ経験豊かな職人が現場調査をおこない、工事が必要な場合には、分かりやすく丁寧にご説明
させていただきます。お見積りは勿論無料なので、お気軽にお問合せくださいませ。